Dカーネギーの『人を動かす』を紹介します。
『人を動かす』は人に動いてもらう本ではありません。
相手が気持ちよく動いてくれる本なんです。
成功をしている人が必ず読んでいるという名著を紹介します。
最初にこの本の読み方からお伝えしますね。
どうぞ最後までお付き合いください。
\漫画で読みたい方はこちら/
Dカーネギー『人を動かす』を紹介!
Dカーネギー『人を動かす』を紹介します。
著者であるDカーネギーがなんども繰り返し読むようにはっきりと伝えています。
この本の原則は、カーネギーでさえも、”実践するのが難しい”と言っている本だから、何度も読まなくては実践ができないんです。
\何度も繰り返し読むかたはこちら/
Dカーネギー推奨の『人を動かす』の読み方
Dカーネギー推奨の『人を動かす』の読み方を紹介します。
『人を動かす』の読み方
- 最初は速読します。
- そして繰り返し読みます。
- 読むだけではなく時には立ち止まってこの本のことを考えてみます。
- 本に線を引いたり、メモを取ります。
- 実践できているかどうか定期的にチェックします。
\何度も繰り返し読むかたはこちら/
「もしも蜂蜜を集めたいなら蜂蜜の巣箱を蹴とばすな』
人を動かすことは容易なことではありません。
なんて言ったって人は変えられないと言われているのですから。
例えば、凶悪犯でも、自分のことは正しいと考えている・・・という衝撃的な話から始まります。
どんな悪いと言われる人でも、自分が正しいと思っているんです。
驚きますよね。
だから人を動かすのにはその人は自分は間違えていないということを理解してあげます。
人を動かす三原則を実践したら自分を認めてくれたと認識して、自分を認めてくれた人のために動いてくれるのです。
「人を動かす三原則」
- 批判も非難もしない
- 苦情も言わない
- 率直で、誠実な評価を与える
- 強い欲求を起こさせる
人は誰でも他人から高評価を受けたいと思っている
偽りのない心からの賞賛を願っているから、そのことを踏まえた上で、自ら動きたくなるような気持ちをおこさせることが大事なんです。
犬に学ぶ、人に好かれる六原則
友を得るためには、わざわざこの本を読まなくても良いそうです。それは・・・世の中で一番優れた達人のやり方を学べばOKなんです。
その達人はワンちゃん♪犬なんです。
尻尾をふって飛びついてくる。
全身全霊で自分のことが大好きだと表現してくるあの様子にこそ学ぶべきとこの本では伝えています。
要点をまとめました。
「人に好かれる六原則」
- 誠実な関心を寄せる
- 笑顔で接する
- 名前は、当人にとって、最も快い、最も大切な響きを持つ言葉であることを忘れない
- 聞き手にまわる
- 相手の関心を見抜いて話題にする
- 重要感を与える – 誠意を込めて
人は本来、自分にしか興味がないものなのだから、
聞き上手になって、相手が喜んで話してくれるような質問をするようにします。
相手自身のことや相手の得意にしていることを話してもらいます。
この本を読んでいると、「人の名前を覚える」ってすごく重要だということが判ってきます。
名前を憶えてもらえるということは興味を持ってもらえたことだから。
まだまだあるその他の原則
一度にはお伝えできないこの本の内容です。
原則もまだまだあります。
「人を説得する十二原則」
- 議論に勝つ唯一の方法として議論を避ける。
- 相手の意見に敬意を払い、誤りを指摘しない。
- 自分の誤りをただちにこころよく認める。
- おだやかに話す。
- 相手が即座に’イエス’と答える問題を選ぶ。
- 相手にしゃべらせる。
- 相手に思いつかせる。
- 人の身になる。
- 相手の考えや希望に対して同情を持つ。
- 人の美しい心情に呼びかける。
- 演出を考える。
- 対抗意識を刺激する。
「人を変える九原則」
- まずほめる。
- 遠まわしに注意を与える。
- まず自分の誤りを話した後、相手に注意を与える。
- 命令をせず、意見を求める。
- 顔を立てる。
- わずかなことでも、すべて、惜しみなく、心からほめる。
- 期待をかける。
- 激励して、能力に自信を持たせる。
- 喜んで協力させる。
そして、「幸福な家庭を作る七原則」というものまであるんです。
家庭編が一番大事なことかもしれませんね^^
「イエスと答えられる問題を選ぶ」は、「ソクラテス式問答法」とも呼ばれる古典的な手法なんです。
相手を批判をしてしまうと問題がこじれてしまいます。
最初は相手にイエスばかり言ってもらう質問ばかりをして、できるだけノーと言わせないようにするのがポイントです。
『人を動かす』をまとめた動画も紹介しますね。
BOOKレビュー『人を動かす』D/カーネギー
生きていくためにも職場で円滑に働くためにも必要な教え
相手を論破をしてはいけない。。。。
今までの失敗に納得できます。
議論を避けることが議論に勝つ方法
そして、セールスに押し切られない方法も♪
生活の知恵が身に付いちゃいます。
Dカーネギー『人を動かす』を紹介!ブックレビューのまとめ
- 何度も読んで自分に落とし込んでより良い人生を歩いていくための本です。
- 『人を動かす』は人に動いてもらう本ではありません。
- 相手が気持ちよく動いてくれる本。
- 成功をしている人が必ず読んでいるという名著
\漫画で読みたい方はこちら/
\何度も繰り返し読むかたはこちら/

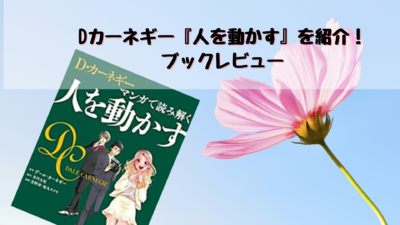




コメント